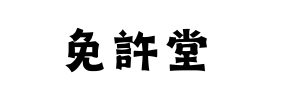大型自動車免許の仮免許は、免許センター構内での技能試験に合格することで取得できます。
試験の合格基準は、持ち点100点からの原点方式で、完走時に60点以上残っていれば合格となります。
しかし、実際には完走できてもすぐに合格できず、何度か挑戦して初めて合格するケースも珍しくありません。
公式な基準はありますが、試験官の本音としては**「この受験者の助手席に公道で安心して乗れるか」**が、最も重要な判断基準の一つだそうです。
一般の公道では構内ほど道幅が広くないため、運転がフラフラしていたり、狭い道で立ち往生してしまうと事故につながる可能性があるからです。
※情報は2025年1月現在の神奈川県免許試験の内容に基づきます。
運転時間について
私の受験回数は合計8回で、そのうち4回が完走でした。
練習は主に以下で行いました:
- 戸塚自動車学校:50分 × 5回
- 免許センター:50分 × 2回
これだけ運転すれば、運転技術は確実に上達します。
ちなみに教習所に通う場合の練習回数は以下の通りです:
- 中型一種(8t限定MT)所持者:50分 × 8回
- 普通一種MT所持者:50分 × 12回
私の場合は中型一種を既に所持していたため、50分 × 5回で済みましたが、費用対効果で考えると効率的とは言えない状況でした。
受験のたびに「教習所に戻ろうか」と迷うこともあり、精神的にプレッシャーを感じる瞬間もありました。
苦手な部分
私が特に苦手とした課題は以下の2点です。
- クランクの右曲がり
- 左前輪の攻めが不十分で、右後輪が脱輪しやすくなります。
- ここは何度も練習して感覚を掴む必要がありました。
- 左折
- 左後輪が縁石から離れすぎてしまい、コース取りが少し不安定になります。
それ以外の課題は、1回の練習で十分対応可能で、大きな問題にはなりませんでした。
完走時の状況
コースを無事に走り切って完走しても、その場で合格が伝えられることはありません。
完走後は、試験官からワンポイントアドバイスを受けます。
- 左折時には丁寧にスピードを落として走行することを指導されました。
- クランクでは停止した状態でハンドルを切らないことを注意されました。
それ以外の部分は特に問題なしとの評価でした。
合格発表の流れ
大型仮免許試験の合格発表は、13番の技能試験受付前で行われます。
- 受験者は順番に呼び出され、合格していればその場で収入証紙を購入
- 仮免許発行の手続きを進めるよう指示されます
- 収入証紙を用意できれば直ちに仮免許が発行されます
仮免許は通常の免許証とは異なり、ペラ紙で簡易的に発行されます。
仮免許受験時に作成した申請書類も返却されます。
なお、試験の点数自体は教えてもらえません。
仮免許取得後の流れ
- 仮免許の有効期限は6か月です。
- 本免許(大型一種免許)取得には再度書類作成と適性検査(視力検査)が必要です。
- 午前中の仮免試験に合格した場合、午後に書類作成と適性検査をまとめて行うとスムーズです。
- 本免許試験に挑戦するには、事前に路上練習を行い、その証拠として書類を作成する必要があります。
まとめ
- 大型仮免許の取得は単なる技能試験だけでなく、試験官が助手席に安心して乗れるかどうかを重視している点が特徴です。
- 完走できても合格できない場合があり、練習や受験回数の積み重ねが重要です。
- 苦手な課題を重点的に克服し、ワンポイントアドバイスをしっかり実践することが合格への近道です。
- 仮免許取得後は6か月以内に路上練習と書類作成を進め、本免許試験に備える必要があります。